自分で考えて選択できる、自立した大人になってほしい
子どもが生まれたとき、このように考えた親御さんも多いのではないでしょうか。
しかし、親がどう行動すれば子どもが自立できるのかなんて、誰に教わるわけでもないし全くわからないな、と私は感じていました。
そこで、私は少しでも参考になればと思い1冊の本を手にしました。
それが、
自分でできる子に育つ ほめ方𠮟り方
著・島村華子
出版・Discover
です。
様々な媒体で話題にもなった本なので知っている方も多いと思います。
妊娠中にこの本を読み、0歳の娘への声掛けでこの本で学んだことを実践しています。
「0歳なんてまだ会話もできないから、できることないのでは?」
ここまで読んで、そう思われた方もいらっしゃるでしょう。
確かに0歳の赤ちゃんに対して叱らなければならないことなんてなく、ほめるにしても赤ちゃんに理解はできないでしょう。
しかし、私はなるべく早いうちにこの本の内容を知り、育児に生かしていただくことをおすすめします。
その理由を、本の内容にも触れながら紹介いたします。
子どもへの愛情とは何かを考える
「こうなってほしい」と親が子どもに対して思うことは愛があってこそであり、誰しも理想像は持っているものと思います。
しかし、ここで子育てにおける愛情というものを正しく認識しておかないと、子どもの自主性の成長を阻害してしまいかねません。
ここで重要なのは、子どもを一人の人間として尊重し、子どもの行動や考え方の理由をまず考えて接してあげることです。子どもの行動を親の価値観だけで頭ごなしに悪いと決めつけるのではなく、なぜその行動をとったのか、なぜ泣いたり怒ったりしているのかにきちんと向き合うのです。
つまり、叱る・褒めるに共通して言えるのは、人中心(行動、容姿)の声掛けではなく、プロセス(努力、理由)に対して声をかけてあげることが大切です。
言い方のクセはすぐには直らない
理屈ではわかるけれど、いざ子どもと向かい合った際に言い方のクセというものは意識していても出てしまうもの。
例えば、「ダメ」「違う」などの否定的な言葉は、子どもが脅威に感じてフラストレーションが爆発しやすい状態になってしまうので、極力使わないよう心掛けることが大切です。
しかし、私は夫の家事のやり方に不満を抱いた際にとっさに「違う違う!」と発してしまっていたり、結構な頻度で否定的な言葉が口から飛び出してしまっています。子育てでもつい口にしてしまいそうでクセを修正するのも結構難しいな、と感じました。
家族間だけでなく、会社内でも、プロセスを褒めようと思っていてもとっさに気の利いた言葉が出てこないので、なかなか思うように実践できていないことが多いです。
日々の継続あるのみ
0歳の赤ちゃんでも、親とのコミュニケーションは言葉の発達に必要不可欠です。
まだプロセスを褒めたり叱ったりする機会はほとんどないかと思いますが、赤ちゃんとのスキンシップを通して、褒め方叱り方の練習なら日常的に実践可能です。
よく動くようになるとちょっと危ないところに近づいていったりしてしまうこともあるため、その時に言い方のクセを見つけ、もっとよりよい言い方はなかったかと考えてみるだけでも十分練習になります。
また、赤ちゃんだけでなく、大人との会話の中でも実践できます。
仕事だと後輩に指導する際、きちんとプロセスを評価した言葉をかけているか意識してみたり、などなど。
特に、夫など家族に対して心を許しているからこそはつい感情的になってしまいがち。感情的でなく、きちんと説明ができているか日頃から心掛けることで、子育てにおけるコミュニケーションの練習にもなると私は考えます。
まとめ
今回紹介した本には、育児で起こりがちな様々なケースに対する具体的な声掛けの仕方が分かりやすくまとめられています。
とはいえ、本でも触れられていますが、完璧に出来る必要はなく、「今の声かけは良くなかったかも…」なんていちいち気に病む必要はありません。
子どもに対する愛情とは何か。意識するだけでもかける言葉や親の行動は変わっていくものと私は考えます。子育てには正解がないからこそ、コミュニケーションに悩みはつきもの。そんな悩みの手助けになるはずですので、ぜひ、手に取って読んでみて下さい。

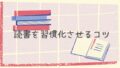

コメント