夫も積極的に育児に参加することが当たり前となってきた昨今。
私の夫も、子どもが生後1か月になったあたりから2か月の育休を取得しました。
身体も完全には回復していない中、育児で手一杯となっていた私にとっても夫の育休取得は大変助かりましたし、夫も育休を取得したことで「視野が広がった」と言っていました。
今でこそ二人で乗り越えた産後すぐの大変な時期はいい思い出として語ることができますが、二人とも育休を取っていた時期は毎日が満身創痍でした。
二人で子育てをすることは子供にとっても良いことのはずですが、そのあまりの大変さから夫婦仲に亀裂が入ってしまうことも少なくないようです。特に、夜間授乳が必要な時期は双方寝不足になりしんどい日々がしばらく続くため、「いつ終わるのか…」と二人ともノイローゼ気味になりました。
しかし、我々はお互いに疲労もストレスもありましたが、関係が険悪になるようなことはなく(自分でいうのもなんですが)産後も産前と変わらずとても仲良しです。
家族が増え、辛い日々も協力して乗り越え楽しい毎日を夢見ていたはずなのに、育児をきっかけに夫婦仲が悪くなってしまっては本末転倒です。
そうならないために、ストレスも多い夜間授乳の時期を夫婦で乗り越えるコツを紹介したいと思います。

夜間授乳の時期の家事・育児の分担のコツ
苦手なことを相手に強要しない
「男の人は、夜に赤ちゃんが泣いても起きない」は本当です。
一日の中で最も孤独で辛い時間帯である夜間、二人で起きて一緒に授乳や寝かしつけを行ったり、妻が休み夫がワンオペで頑張るやり方を取っている家庭も多いと思います。
しかし、夫が日中家事育児を頑張って夜は休む、という体制で挑んだ方が、相手にいら立ちを覚えなくて済むと私は考えます。これは、母乳外来でお世話になった助産師さんもおっしゃっていたことなのですが、男性は夜寝ないとやっていけない生き物らしいです。
我が家も最初のころは、夫も夜間一緒に起きて交互に赤ちゃんの対応をしていましたが、そうすると夫は日中に全く元気がなくなってしまっていて、育児が精いっぱいで家事が全くできなくなってしまいました。日中の会話もなくなり、育児を楽しむ余裕がありませんでした。
そこで、私は赤ちゃんが泣けば何時だろうと起きれるのですが、夜間は夫を起こさないで一人で対応することにしました。そのかわり、日中私がしっかりお昼寝できるよう家事育児のほとんどを夫に託しました。
その結果、夫はまとめて夜眠れるようになったおかげで日中の活気が少し戻り、私もお昼寝ができ日中夫と会話も楽しめるので、夜間二人体制で育児していたころより体が楽になりました。
自分を見つめなおし、パートナーを観察する
真面目な人ほど頑張りすぎてしまい、体が悲鳴を上げていることに気づきづらいです。
それは夫にも言えることです。育休を取って、「夜間も手伝うよ」と言ってくれるような優しいパートナーならより一層、無理をしていないか一日の内ほんの少しでもいいので気にかけてあげてください。
自分のことで精いっぱいですが、自分と相手、どちらも疲れすぎていないか、睡眠をとれるタイミングなどでちょっと振り返るだけでも、夫婦に合った分担方法を見直すことができます。
私の場合は、日中の会話が少なくなり夫の顔色が明らかに悪くなっていることに気づいてから、育児の体制を見直し自分たちのベストな方法を見つけることができました。
夫婦仲が良いと赤ちゃんも落ち着きます。せっかくの育児休暇、お互いに大変さを理解できる機会だからこそ相手を思いやって、辛い時期をともに乗り越えてくださいね。


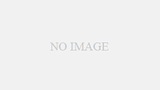
コメント